基調講演

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 事務局長 / 社会活動家
1989年生。シェアリングエコノミーの普及に従事。シェアの思想を通じた新しいライフスタイルを提案する活動を行うほか、一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局長、厚生労働省・経済産業省・総務省などの政府委員も多数務める。また2018年ミレニアル世代のシンクタンク一般社団法人Public Meets Innovationを設立、代表に就任。ほかNewsPicks「WEEKLY OCHIAI」レギュラーMC出演やコメンテーター、新しい家族の形「拡張家族」を広げるなど幅広く活動。著書「シェアライフ-新しい社会の新しい生き方(クロスメディア・パブリッシング)」
分科会


CRファクトリーが「コミュニティマネジメントの理論」をつくる上で最も参考にしてきた3団体。強くあたたかい組織・コミュニティをつくりながら、多くの人たちの「参加」をつくってきた圧倒的にすごい3団体。そこにはどんな考え方やマネジメントの秘訣があるのか。大大大注目です!!

NPO法人チャリティーサンタ 代表理事
1人旅を通じて「恩返しではなく恩送り」という価値観を知り、2008年にチャリティーサンタを開始。27都道府県39支部で活動中。建築設計事務所、ITフリーランス、株式会社サイバーエージェントを経て、2014年より現職。福岡県出身。国立有明高専 建築学科卒。

こんな時代だからこそコミュニティを育もう!

NPO法人コモンビート 事務局長
コモンビートのミュージカルプログラム参加をきっかけに、表現を手段にした教育の可能性や非営利組織運営に興味を持ち、2013年から職員として参画。コロナ禍において、市民の表現活動の価値の探求や、オンラインでの血の通ったコミュニケーションやコミュニティ作り、多様な関わり方のできる組織デザインに従事。

一人一人異なる「しっりくる」答え。その違いを楽しみながら、この時代のコミュニティのあり方を共に学ばせていただこうと思います。よろしくお願いします!
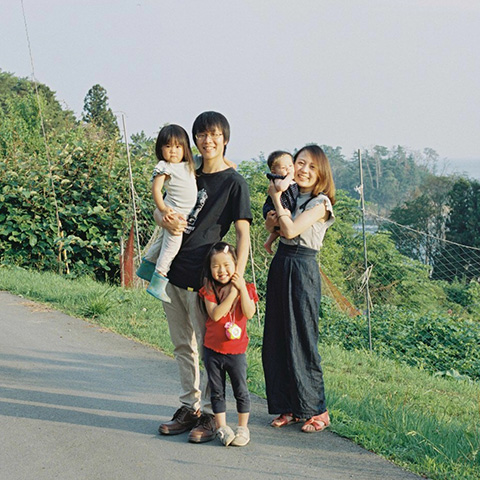
NPO法人SET 理事長
1998年12月23日茨城県つくば市生まれ、現在岩手県陸前高田市広田町在住。NPO法人SET (2019年内閣総理大臣賞受賞)の理事長。元岩手県陸前高田市議。NPO法人高田暮舎理事。二つの大学で教鞭を執る。次に登る山は政策起業家。好きな言葉は「できるかできないかじゃなくて、やるかやらないか」
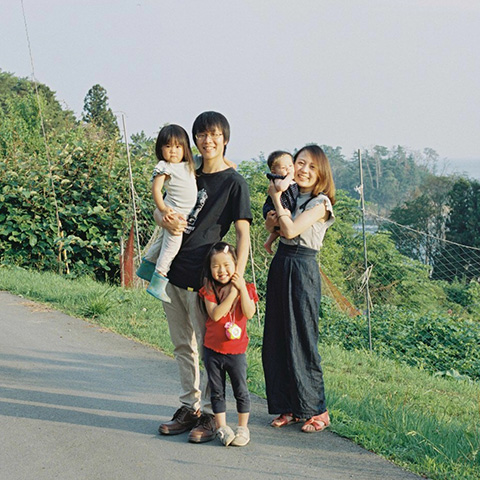
豊かなコミュニティを考え、作ることは、実は一人一人の豊かな人生を考えることだと思っています。ぜひそんなお話を皆さんとできればと思っています。


子育てや子どもの育ちを社会で・地域でどのようにつくっていくのか。子育て期における「つながり」や「コミュニティ」の最適なかたちとはどのようなものなのか。戸塚と松戸での現場実践と、学術的な知見との掛け算で、深くて多角的な議論になること間違いなしです。お楽しみに。

早稲田大学 教授
現代社会の人間関係や孤立をテーマに調査・研究を行っている。主たる著作に『友人の社会史』(晃洋書房、2021年)、『孤立不安社会』(勁草書房、2018年)、『つながりづくりの隘路』(勁草書房、2015年)がある。

コロナ禍でつながりに対する見通しが不透明になるなか、今一度、ひととつながることについて考えられればと思います。

特定非営利活動法人まつどNPO協議会 理事
千葉県松戸市の中間支援施設でセンター長や高齢者の暮らしを地域で支える生活支援コーディネーターの役割を担っている他、自身が代表を務める団体にて民間学童を運営するなど、「子ども若者が未来に希望を持てる社会」を目指して活動中。2020年度より休眠預金の実行団体としてコンソーシアムの運営に関わっている。

先行きが見えない今だからこそ、少し立ち止まって自分たちにとって目指したい社会のあり方に向き合ってみる。皆さんと一緒にそんな時間を過ごせると良いなと思っています。
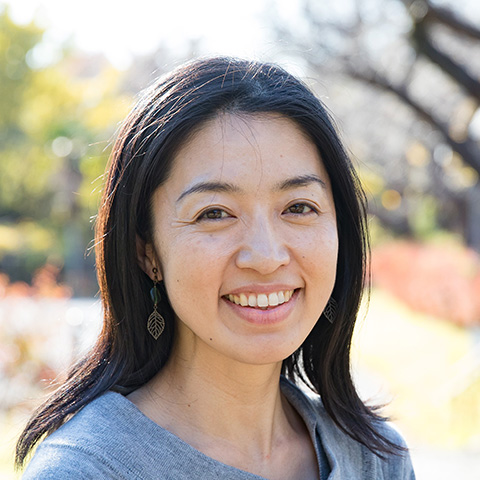
認定NPO法人こまちぷらす 理事長
トヨタ自動車にて海外営業等に従事した後、第一子出産直後に感じた育児における孤独感や救われた経験から、2012年に退社し当時のママ友数人と団体を立ち上げる。現在横浜にてスタッフ約50人・こまちパートナー約180人とともに「こまちカフェ」を拠点とした対話と出番の場づくり、企業との協働プロジェクト等展開。
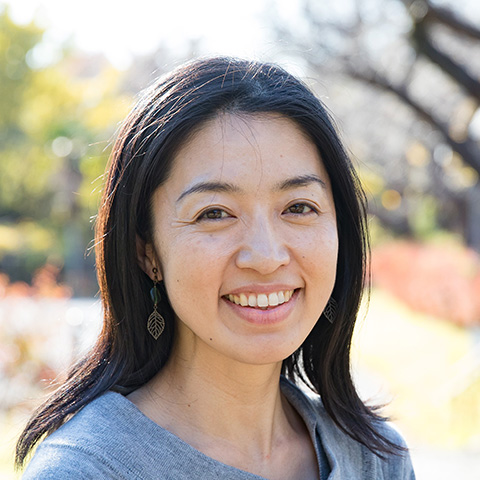
ここちよい「つながり」ってなんだろう?参加される皆さんが特にここ最近どんな風に感じたり考えているのか聞いたり一緒に話たりできるのを楽しみにしています!


障がいや難病のある本人や家族にとって、「つながり」や「コミュニティ」があることはとても重要なことです。そして、それが地域や人々のつながりの中で広がったりあたたまったりしていくことが望まれます。「つながり」と「コミュニティ」が豊かになることは、”生きること”を豊かにしてくれるのです。障害・難病の現場にいると本当にそう思います。

社会福祉法人いぶき福祉会 専務理事
1969年京都市生まれ、神戸育ち。大学で心理学を学ぶ。企業退職後に社会福祉士を取得。1997年に社会福祉法人いぶき福祉会に入職する。障害福祉の枠をこえたマーケティングを展開。人と人とのあいだをつなぎ、新しい価値を創発し、誰もが安心して暮らせる寛容な社会の実現に取り組んでいる。

たくさん対話をしましょう!新しい物語を綴り始める一日に!
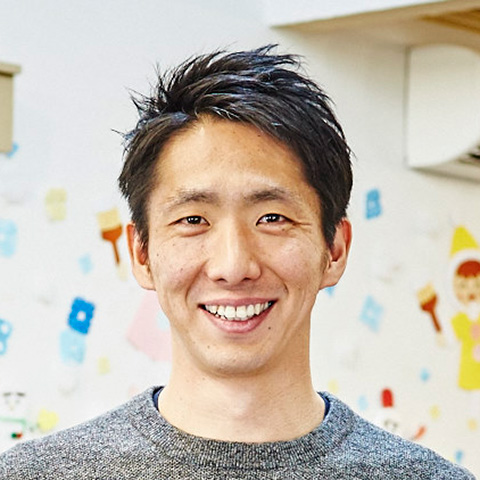
一般社団法人Burano 理事
茨城県古河市生まれ。大学卒業後、新卒で株式会社リクルート入社。
その後、同社を退職し地方統一選挙に市議会議員候補者として出馬し2位当選を果たす。議員としてまちづくりを行う一方で経験やスキル不足を実感し、自らを鍛えるため人事コンサルティング会社JAMに入社。2017年、第二子に重度の障害があったことがきっかけで、重度の障害児と家族を支える非営利組織Buranoを立ち上げる。
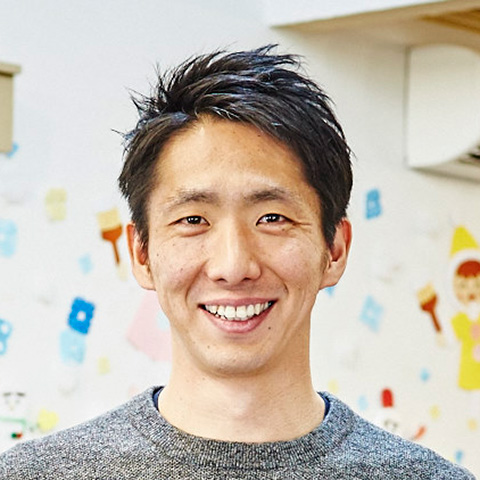
これまでのBuranoの取り組みが少しでも皆さんにとっての気づきであったり、ヒントになれば嬉しいです。

特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ 代表理事
1988年愛知県生まれ。筑波大学在学中に、現つくば市長である五十嵐立青とともに、団体を設立。障害のある人たちが働く農場「ごきげんファーム」を運営。現在は、有機野菜の栽培をする農場、平飼い養鶏に取り組む農場、水稲に取り組む農場の3農場を運営。その他に、障害のある人が暮らすグループホームや、発達障害児を支援するデイサービスなどを運営している。

農業や障害のある人たちの暮らしに関心のある皆さん、お話できることを楽しみにしております!!


コミュニティキャピタル研究会では、「理想的なコミュニティの要件とは何だろう?」という問いから研究を始めて、指標となる3つの因子を導き出しました。それは「①理念共感と貢献意欲」「②自己有用感」「③居心地の良さ」の3つです。毎年この調査に参加してくれているチャリティーサンタとSETを交えて、研究という切り口で「コミュニティを科学する」分科会。ぜひご注目ください。

上智大学経済学部 教授 / コミュニティキャピタル研究会 / みかんハウスオーナー
経済学と心理学を融合した行動経済学の知見を応用して様々な社会課題の解決方法を研究しています。2012年から人間関係が希薄になりコミュニティが脆弱になった現代社会の問題をコミュニティキャピタル研究会で研究しています。研究を通じて豊かな人のつながりのある幸福な社会づくりに貢献したいです。

人類は争いもしてきましたが、その繁栄はまさに人と人との支え合い、助け合いによってもたらされてきました。それは簡単なことのようで難しい。皆さんと一緒に考えてみたいと思います。よろしくお願いします。

NPO法人チャリティーサンタ 代表理事
1人旅を通じて「恩返しではなく恩送り」という価値観を知り、2008年にチャリティーサンタを開始。27都道府県39支部で活動中。建築設計事務所、ITフリーランス、株式会社サイバーエージェントを経て、2014年より現職。福岡県出身。国立有明高専 建築学科卒。

こんな時代だからこそコミュニティを育もう!
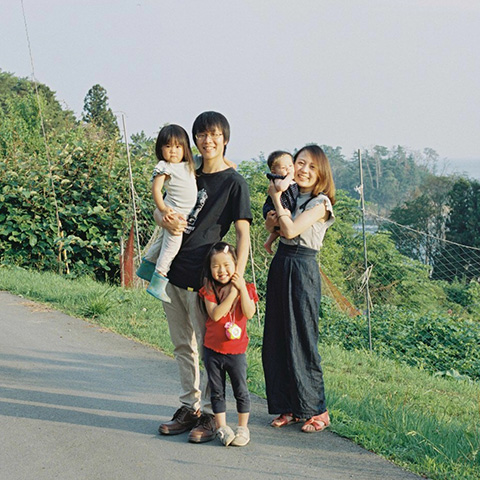
NPO法人SET 理事長
1998年12月23日茨城県つくば市生まれ、現在岩手県陸前高田市広田町在住。NPO法人SET (2019年内閣総理大臣賞受賞)の理事長。元岩手県陸前高田市議。NPO法人高田暮舎理事。二つの大学で教鞭を執る。次に登る山は政策起業家。好きな言葉は「できるかできないかじゃなくて、やるかやらないか」
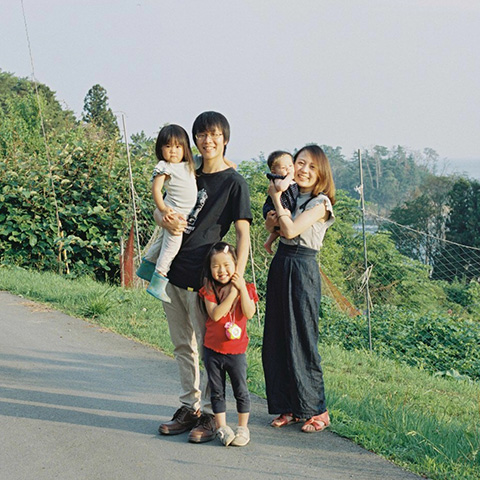
豊かなコミュニティを考え、作ることは、実は一人一人の豊かな人生を考えることだと思っています。ぜひそんなお話を皆さんとできればと思っています。


この3人が一つの分科会に同時に入ることがかなり奇跡的で、今から化学反応や相乗効果が楽しみでなりません。「グローバルシチズンシップ」「混ざり合う社会」「ありのままの自分」。いろいろなキーコンセプトを交ぜながら、コミュニティのあり方や個人の生き方などについて白熱した分科会になること間違いなしです。

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 代表理事/ファウンダー
2012年に(一社)GiFTを設立。現在は「トビタテ!留学JAPAN」高校生コース事前事後研修やアジア7カ国を舞台にした海外研修等、SDGs、グローバル・シチズンシップ育成に関するプロデュース、研修、講演等を行っている。2年前に鎌倉に移住。自然と文化とのつながりを味わう時間を過ごしている。

GiFTが取り組むグローバル・シチズンシップ育成の中でも「多様性」は大切なキーワードです。文化、性別、国籍、言語、民族、身体的な違い、生まれ育った環境、受けてきた教育、さまざまな多様性があります。そして、自分の中にも人生の中にも「多様性」があります。多様性を楽しみ、繋がりに感謝すること。そうした対話を深めていけたらと思います。

NPO法人日本ブラインドサッカー協会 専務理事・事務局長
特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会(JBFA) 専務理事 兼 事務局長/国際視覚障がい者スポーツ連盟(IBSA)理事/一般財団法人International Blind Football Foundation 代表理事。「サッカーで混ざる」をビジョンに掲げ、サステナビリティをもった障がい者スポーツ組織の経営を目指す。

社会環境が大きく変化しているいま、容易に「分断」されやすくなっていることを感じます。このような状況だからこそ、多様性を尊重する意味はなんなのか、みなさんと一緒に考えたいと思います!

認定特定非営利活動法人ReBit 代表理事
LGBTを含めた全ての子どもがありのままで大人になれる社会を目指し、ReBitを設立。学校/行政/企業でのLGBTやダイバーシティ研修、キャリア支援、国内最大級のダイバーシティ・キャリアフォーラム開催を行う。ダボス会議が選ぶ世界の若手リーダー、オバマ財団が選ぶアジア・パシフィックのリーダー選出。

マイノリティの子どもたちにとっても、今回のテーマである、ここちよい「つながり」ができることで、しっくりくる「生き方」が見つかる機会が全国で増えたらいいなと思います。ぜひみなさんといっしょに考えさせてください!


「医療」や「健康」において、「つながり」と「コミュニティ」が果たす役割は実はとても大きいのです。「つながり」や「コミュニティ参加」の度合いによって、抑うつ・要介護・認知症・死亡率が変わってくることは段々と知られてきています。今回の分科会の登壇ゲストお二人はお医者さん。医師が見つめる「つながり」と「コミュニティ」の話をぜひ一緒に聞いてみましょう。

一般社団法人 CAN net 代表理事 / 腫瘍内科医師
自身が、患者・家族・医師としての経験から新しいサービスの必要性を感じ2013年「誰もが病気になっても自分らしく生きられる社会をつくる」一般社団法人CAN netを立ち上げ。北海道帯広市で医師として働きながら、病気の当事者だけでなく様々な人が関わる「大人の部活動」「サードプレイス型NPO」の運営を旭川、札幌、帯広、東京の4都市で行っている。主なプロジェクト「チームがんコンシェルジュ」「がん×認知症プロジェクト」「北海道医療美容研究会」「医療×LGBT」など。

目には見えないけれども人の生き方・幸せに重要な「人のつながり」「コミュニティ」について一緒に考える機会になったら嬉しいです。
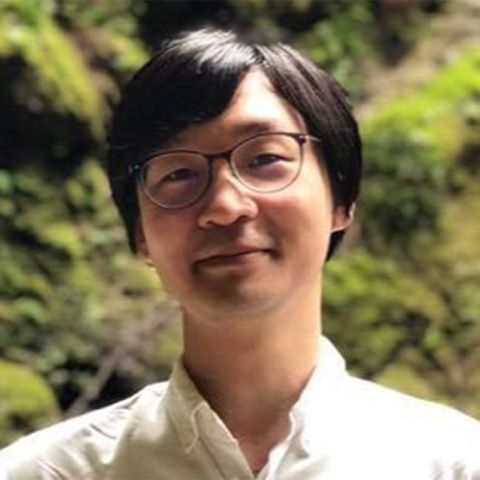
王子生協病院 医学教育アドバイザー / 家庭医 / コミュニティドクター
東京と栃木を行ったり来たり。家庭医として病院・診療所ではたらき、コミュニティドクターとして街をフィールドワークすることを通して、そのひとらしく最期まで暮らすことについて探求することを仕事にしている。また、そこで得た知恵を生かして、地域をケアする人の学びを支援する教育・研究活動をしている。
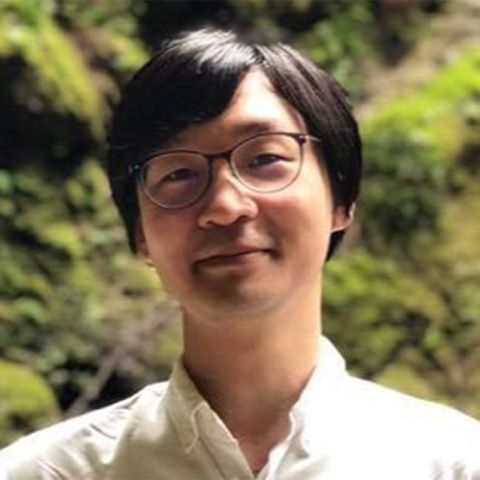
ウィズコロナで医療が誰にとっても身近になった今だからこそ、感染予防だけではない、医療とコミュニティの健全な関係を一緒に考えましょう。

東京医科歯科大学 介護・在宅医療連携システム開発学講座/一般社団法人日本老年学的評価研究機構 助教/理事/医師(家庭医・訪問診療医)
疫学・公衆衛生の専門家としてマクロな視点での研究や実践と、家庭医としての臨床・教育・マネージメントのミクロ・メゾ活動の両立のバランスを模索中。臨床医、また地域の一員として出会う目の前の人たちが最期まで「自分らしく」いられる地域の在り方、専門職のサポートの在り方、制度的サポートの在り方に関心を持ち、日々実践・研究中。

一生医療を必要としない人もいる。でも、誰しも(多くは望まないけれど)医療が必要になるときが来ることがある。日々の当たり前のコミュニティの中での「最適な医療のあり方」とそれを実現するために必要なことについて、皆さんと一緒に考えてみたいです。
※基調講演・分科会のテーマ/ゲストは、状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。




